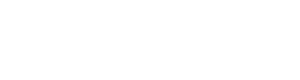一般的な情報
Q.TSUBAME4.0 を利用するための、基本的な情報はどこを見ればよいですか。
A. TSUBAME4.0のご利用にあたりましては、以下の手引きなどをご参考になさってください。
TSUBAME4.0 クイックスタートガイド
TSUBAME4.0 利用の手引き
TSUBAME4.0 FAQ
TSUBAMEポータル利用の手引き
TSUBAME共同利用 利用講習会資料Q.FAQを見てもわからない場合には、どこへ連絡したらよいですか。
A. TSUBAME共同利用 利用者および HPCI 産業利用 利用者は こちら からお問い合わせください。
TSUBAME相談窓口 は基本的に学内ユーザーの問い合わせ窓口となっておりますが、
学術利用の利用者や共同研究の学外利用者からの問い合わせにも対応いたします。
利用可能なサービスに関して
Q.TSUBAME共同利用では有償アプリケーションは利用できますか。
TSUBAME共同利用で利用可能なアプリケーションを教えてください。A. TSUBAME共同利用では、インストール済みの有償アプリケーションから一部をご利用いただけます。
学外利用者が無償でご利用いただけるアプリケーションは以下の通りです。
- OS(Red Hat Enterprise Linux 9.3)、ジョブスケジューラ(AGE)
- gcc、Intel (oneAPI)、nvhpc (PGI)、CUDA、Forge 等開発環境
- Gaussian 16、GaussView
- Amber (学術利用のみ)
- TSUBAMEに導入済みのフリーソフトウェア (アプリケーション一覧 の "フリーソフトウェア" の項を参照ください)
上記以外の一般的な商用ソフトウェア(ISVソフト)を利用する場合は、ベンダーからライセンスを取得していることが条件となります。
VASP は学術利用のユーザーは利用可能ですが、産業利用のユーザーはご自身でバイナリを用意していただくことになります。
ライセンスについては配布元にお問合せください。Q.GPU対応のアプリケーションを教えてください。
A. TSUBAMEに導入済みアプリケーションのGPU対応状況については、こちらの "GPU対応" の欄をご確認ください。
Q.libcuda.so.1 => not found がでますが?
A. コマンドを実行した際に
error while loading shared libraries: libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
と表示される場合は、ログインノードで実行していませんか? 計算ノードを確保したうえで実行してください。
TSUBAMEのログインノードには GPU が搭載されていません。
また、ログインノードでは負荷の高いプログラムの実行はお控えください。Q.CUDA で GPU を割り当てるには?
A. CUDAを利用し GPU を指定する場合は環境変数 CUDA_VISIBLE_DEVICES を使用します。
TSUBAME計算ノード (node_fの場合) はデバイス番号が 0-3 までの4つのGPUが利用可能です。
以下のように指定することで各GPUを利用することができます。
・GPUの0番を指定する場合
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0
・GPUの0~3番を指定する場合
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3
例:
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3また、CUDA API の cudaSetDevice() で指定することも可能です。
詳細は こちら をご参照ください。Q.Mac で Xアプリケーション(GUI)が動作しません
A. Mac から TSUBAMEにログインして COMSOL や GaussView などの Xアプリケーション
を実行する際、Mac の XQuartz を使用した場合 GUI が正しく表示されない場合があります。
下記の設定を行ってから TSUBAME のアプリケーションを実行してください。・Mac 側での設定:
sudo defaults write org.macosforge.xquartz.X11 enable_iglx -bool true
・TSUBAME側での設定:
export USE_MESAGL=1これらの設定により OpenGL を MESA にて対応し表示することが可能となります。
一般的な X アプリケーションの不具合につきましては こちら をご参照ください。
FAQ TopQ.1口の利用料金を教えてください。
Q.1口=400ノード時間相当で、TSUBAME4.0 はどれくらい使えますか。
(1口は 400ノード時間相当で 400 TSUBAMEポイントです)A. 1 TSUBAMEポイントで、標準ノード node_f (192CPUコア、4GPU、768GBメモリ) を 1時間利用できます。
この400ノード時間相当は、例えば以下のそれぞれの計算資源に相当します。
- 1 ノードを1日4時間利用で100日間使用可能。
- 2 ノードを1日4時間利用で 50日間使用可能。
- 5 ノードを1日8時間利用で 10日間使用可能。(5nodes × 8hours × 10days = 400 ノード時間)
- 予約システムを利用する場合は 80ノードで 4時間利用可能 (閑散期) 予約係数 1.25倍となります
- 400 GPU並列を利用するには 100ノードで 4時間使用可能。(400 GPU÷4 ×4時間 = 400 ノード時間)
Q.TSUBAMEポイントを確認する方法を教えてください。
A. TSUBAMEポイントは以下の方法で確認できます。
Q.TSUBAMEポイントを追加したいときはどうすればいいですか
A. TSUBAMEポイントが不足した場合は 提出様式集の "6b .計画変更(利用口数追加)申請書"
を提出してください。その際、請求書発行日と支払期日につきましては事前にご相談ください。
FAQ 口数が足りなくなりました もご参照ください。
なお、口数追加が承認された時点でポイントは追加されます。
ファイルシステムに関して
Q.グループディスクの設定を変更(増、減)したいのですが
A. ハードディスクは 1TB/1年 6ノード時間、SSDは 100GB/1年 2.4ノード時間にて課金されます。
TSUBAME4.0よりグループディスクの容量は、課題責任者が設定することが可能です。
ディスク課金についてQ.処理が中断し計算ノードの /scr にデータが残ってしまいました
A. 原則として SSD に書き込まれたデータはユーザのプログラムにより削除していただくことになっておりますが、
プログラムの中断などにより /scr にデータが残った場合は、システムにより /scr のデータを削除しております。Q.大容量のデータを転送したいときはどうすればいいですか。
A. 比較的小さなファイルの転送につきましてはログインノードをご利用ください。
比較的大きなファイルを転送する場合は、qrsh などでノードを確保したうえで転送を行ってください。
学内のユーザーの場合はこちら をご参照ください。
TSUBAME4.0では計算ノードからも外部のインターネットにアクセスすることができます。Q.異なる課題グループ間でデータを移動したいときはどうすればいいですか。
A. HPCI/JHPCN から共同利用への移動や、年度更新による課題名の変更など、
異なる課題グループ間でのデータの移動が必要な際は、
以下のような手順にてデータをコピーすることができます。・ログインノードへ新課題のアカウント にてログイン
・ログインノードで旧課題から新課題のグループディスクへコピー(scp による例)
PC$ ssh <新アカウント>@login.t4.gsic.titech.ac.jp
<新アカウント>@login$
<新アカウント>@login$ scp -r <旧アカウント>@localhost:/gs/{bs fs}/tgX-<旧課題> /gs/{bs, fs}/tgX-<新課題>Q.WinSCP でデータをコピーしたいのですが。
A. 学外から WinSCP を用いてデータを転送する際には ssh-keygen で作成された鍵のフォーマットと異なる秘密鍵を参照する必要があります。 puttygen で鍵の形式を変換し WinSCP で参照するようにします。
こちら も参考にしてください。Q.データがコピーできません。
A. グループディスクの割り当てを確認し、残りの容量を調べてください。
ホームディレクトリは 25GB までとなりますが、グループディスクは 1TB 単位で購入できます。
グループディスクに余裕がある場合でもファイル数の上限を越えると書き込めなくなります。
1TB あたりの最大ファイル数は 2,000,000 ファイルとなります。
以下の方法でご確認ください。
・クオタコマンドを使用する。 $ lfs quota -g tgx-25IXX /gs/{bs, fs}
・t4-user-info コマンドを使用する。
・TSUBAMEポータルで確認する。
ログインに関して
Q.学外からTSUBAMEにSSHで接続できません。
A.TSUBAME4.0へのログインは公開鍵方式のSSHによる接続のみが可能です。
公開鍵の登録はTSUBAMEポータルより行ってください。
TSUBAME4.0 の公開鍵は RSA 形式でなく ed25519 形式を推奨します。
ssh 接続するためには外部へのインターネット接続が可能で、ポート 22 が利用可能であることをご確認ください。
接続先のホスト名、オプションを打ち間違えていないか確認してください。また、自宅など他のネットワークでの接続もお試しください。
FAQ TopQ.学外からTSUBAMEへSSH接続した際に、「Permission denied (publickey).」と出て、ログインできない。
A.TSUBAME4.0へのログインは公開鍵方式のSSHによる接続のみが可能です。
公開鍵が設定されていない可能性があります。TSUBAME利用ポータルより公開鍵の設定を行ってください。
SSHの公開鍵へのアクセス権に問題がある可能性があります。アカウント名とエラーメッセージをご連絡ください。
ホームディレクトリのモードが 777 など所有者以外の書き込みが可能な場合ログインできません。
デフォルトの設定では 700 となります。ご確認ください。
連絡の際は ssh -v オプションをつけて実行し、ログを添付してくださると原因究明に役立つことがあります。
ssh の FAQもご参照ください。
TSUBAME利用ポータルに関して
Q.「このアカウントは無効です。」と表示されログインできない。
A. outlook のメールを利用している場合、ポータルから送られたメール内の URL をアクセスしても
TSUBAMEポータルにログインできない場合があります。
その場合はメール内の URL をコピー&ペーストしてブラウザに直接入力してください。
なお、ポータルから送られたメール内の URL は一度のみアクセスが可能です。
FAQ TopQ.TSUBAME利用ポータルの公開鍵登録にて、「フォーマットエラーのためアップロードできませんでした。」と出る。
A. TSUBAMEポータルに登録する公開鍵の形式は OpenSSH の形式です。
ssh-keygenなどにより公開鍵を作成した場合は ~/.ssh/id_ecdsa.pub ファイルを登録します(ecdsaの場合)。
PuTTYgenの場合は、画面に表示された公開鍵をノートパッドなどにコピペ&保存したファイルを登録してください。
PuTTYgenを使用する際は こちらの記述 も参考にしてください。
共同利用の手続きに関する質問への回答
利用課金に関して
Q.利用課金は消費税込みですか。
A. TSUBAMEの計算機使用料は次のようになります。(令和6年4月1日より改定)
学外(成果公開) 1口 400ノード時間 110,000円(税込)
学外(成果非公開) 1口 400ノード時間 440,000円(税込)
Q.利用課金の分割払いは可能ですか。
A. TSUBAMEの計算機使用料は、一括払いとなっております。
分割払いが必要な場合には、当初口数申請、追加口数申請、再追加口数申請と分割して
口数申請を行ってください。その場合には、請求書は口数申請毎に発行されます。Q.利用課金の見積書がほしいのですが。
A. ご購入予定口数に対応する利用料金のお見積りが必要な場合は、共同利用支援室までお問合せください。
一口の料金表で対応可能な場合はこちらをご利用ください。
課題申請に関して
Q.課題申請の締切はいつですか。
A. TSUBAME共同利用の申請は随時受け付けております。
年度末の申請に関しましては、各年度の2月の第一週末が申請締切となっております。
配分された計算機利用口数は当該年度末に失効し、翌年度への繰越はできませんのでご了承ください。年度途中でも共同利用での提供可能資源量(総資源量の30%)を超過した場合は受付を終了する場合があります。
Q.年度末の課題申請で注意すべき点はありますか。
A. 年度末には申請締切日があります。
TSUBAME共同利用の申請は随時受け付けておりますが、年度末の申請は、採択後の利用期間が短く、
経理処理上の問題もあり、申請締切日を設けています。各年度の2月の第一週末を目途としております。
また、配分された計算機利用口数は当該年度末に失効し、翌年度への繰越はできませんのでご了承ください。
継続して利用される場合の申請につきましては、継続利用の項目を参照してくださいQ.年度末に余った口数は翌年度へ繰り越せますか。
A. 翌年度へは繰り越せません。
配分された計算機利用口数は当該年度末に失効し、翌年度への繰越はできませんのでご了承ください。
Q.利用課金の請求書の発行と支払い期限について教えてください。
A. 利用課金の支払期日は、組織内での支払い手続きの都合に合わせて、
支払期日申請書に、ご希望の支払期日をご記入ください。
なお、令和2年度より請求書の発行日は、毎月20日に設定されました。
20日が休日の場合は翌営業日にて設定をお願いします。
課題が採択されアカウント発行後にはTSUBAMEを利用することができます。Q.課題審査にはどの程度の期間がかかりますか。
課題申請から、利用開始まではどの程度の期間がかかりますか。A. 通常申請で審査ありの場合、審査を専門分野の近い審査員へお願いするため、1カ月程度かかります。
ただし、以下の場合には審査免除となり、1週間程度で速やかに利用開始することが可能です。
・ 共同利用(学術利用)
・ 継続課題申請: ただし、利用概要報告書/成果報告書を期限内に提出するなど、滞りなく実施された課題に限る
・ 実績のある研究グループの課題申請: 終了課題評価が良好であった研究グループの課題申請
・ 小口利用申請(2口まで): これまでTSUBAMEを利用したことがない場合に可能
採択後に追加口数申請が可能であり、3口を越えた追加口数申請に対しては改めて審査を行います。
課題が採択されアカウント発行後にはTSUBAMEを利用することができます。これまでTSUBAMEを利用したことがない場合は、(3口以上の通常申請の場合でも)
まず2口の小口利用申請をお勧めしております。これは、以下のような理由からです。
(1) TSUBAMEが有効に活用可能かの確認(資源配分後の払い戻しは一切できません)
(2) 審査を待たずに、速やかに利用開始していただくため
(3) TSUBAMEを利用しながら追加口数申請の審査結果を待つことが可能2月の申請締切後から3月中の申請の場合は、4月の運用開始まで利用することができません。
メンテナンス中の申請の場合の利用開始は、運用再開後からとなります。Q.年度を跨いだ利用は可能ですか。
A. 採択課題の利用期間は年度末までのため、年度を跨いで利用するには次年度の利用申請が必要です。
継続して利用する研究グループは審査免除となりますので、
「FAQ. 翌年度も継続利用したいのですが、手続きを教えてください。」も合わせてご参照ください。Q.翌年度も同じ課題で継続利用したいのですが、手続きを教えてください。
A. 基本的には、課題申請書を再度 提出いただくことになります。
申請書には、前年で達成できたことと、翌年度で実施する予定の内容を明記してください。また、利用概要報告書/成果報告書を期限内に提出するなど、滞りなく実施された場合は審査免除となります。
そのため、報告書と課題申請書を同時に提出していただく事で、速やかな利用再開が可能です。
4月初旬での利用開始をご希望の場合は、3月下旬に成果報告書および利用申請書を合わせてご提出ください。Q.翌年度に新規の課題で継続利用したいのですが、手続きを教えてください。
A. 基本的には、課題申請書を再度 提出いただくことになります。
新規課題となりますが「実績のある課題グループによる申請」として審査免除となります。
そのため、報告書と課題申請書を同時に提出していただく事で、速やかな利用再開が可能です。
4月初旬からの利用開始をご希望の場合は、3月下旬に成果報告書および利用申請書を合わせてご提出ください。Q.産業利用トライアルユースの申請をしたいのですが。
A. TSUBAME産業利用トライアルユースの事業は平成27年度で終了いたしました。
平成28年度以降も無償で TSUBAME産業利用をご希望なさる場合は HPCI産業利用 をご覧ください。
なお、TSUBAME有償利用をご希望の方は従来通り TSUBAME共同利用(産業・学術) をご利用になれます。Q.利用期間終了後、ディスクへのアクセスはどうなりますか。
A. 翌年度の継続利用申請が認められた場合は、アカウント、ホームディレクトリは継続してご利用いただけます。
グループディスクは年度毎の課題に対して設定されますので、必要に応じてデータを移動してください。継続利用しない場合でも、利用期間終了後3ヶ月間は同じアカウントでログインすることができ、データを参照することができます。ただしジョブの実行はできません。
Q.本年度の外部への提供可能資源量が超過した場合はどうなりますか。
A. 該当年度の外部への提供可能資源量を超過した場合は申請することはできません。
その場合でも小口申請(2口以下)に限り、累計60口を上限に課題申請を受付ます。
HPCI産業試行課題 ではTSUBAME以外のスパコン資源も利用可能です。
他に mdx などもご検討ください。
課題実施中の手続きに関して
Q.・口数が足りなくなりました。
A. 課題実施中に当初割り当てられた口数を消費し、口数を追加する必要が生じた場合は、
様式6b 利用口数追加申請書に必要な口数、請求書発行期日および支払い期日をご記入の上、
提出していただきます。内容についてあらかじめメールにてご確認いただき、
押印した申請書をPDFにてご提出ください。口数追加が承認された時点で追加口数を付与します。
なお、産業利用小口申請で採択された課題で合計利用口数が2口を越える追加口数を申請する場合は、
あらたに課題審査を行うことになります。ご了承ください。参照ページ: TSUBAME共同利用 提出様式および規則等
Q.・課題従事者を追加(削除)したいのですが。
A. 課題実施中にメンバーを新に追加(削除)する必要が生じた場合は、
様式14 利用課題従事者(追加・削除)申請書に必要事項をご記入の上メールにてご提出ください。
メンバー追加の場合は、あわせてエクセルのメンバーリストおよび、みなし輸出の申告書もご提出ください。参照ページ: TSUBAME共同利用 提出様式および規則等
終了後の手続きに関して
Q.•課題終了後の報告書の提出はどうすればいいですか。
A. 課題終了後 30日以内に様式18 利用概要報告書および、様式20 利用報告書を提出していただく必要があります。
成果非公開の課題の場合は、様式19 利用概要報告書(成果非公開) のみの提出となります。
査読付き論文の投稿もしくは特許取得などで成果報告書を公開できない場合は公開延期の対応も可能です。
産業利用および学術利用の所定の様式がありますので、ワード形式にて電子メールにてご提出ください。
4月中に提出できない場合は共同利用支援室までご連絡ください。参照ページ: TSUBAME共同利用 提出様式および規則等
成果公開に関して
Q.•論文公開や特許申請などで成果が公開できません。
A. 課題終了後は終了一ヶ月以内に成果報告書を提出いただくことになっておりますが、
論文発表や特許申請のために成果を公開できない場合は、報告書の公開を延期することができます。
Q.•発表論文に謝辞を載せたいのですが。
A. TSUBAME4.0 を利用した成果を公開する場合は、下記のような謝辞をお願いします。
共同利用成果公開の利用報告書を提出免除にて対応を希望する場合はTSUBAMEの謝辞の記載が必須となります。2024年10月以降の利用による成果の場合は 東京工業大学 を 東京科学大学 としてください。
(From October 2024, Please change the Tokyo Institute of Technology to Institute of Science Tokyo.)
例1 「本研究は、東京科学大学のスパコンTSUBAME4.0を用いて行った。」
"This study was carried out using the TSUBAME4.0 supercomputer at Institute of Science Tokyo."例2 「全ての計算は、東京科学大学のスパコンTSUBAME4.0を用いて行った。」
"The numerical calculations were carried out on the TSUBAME4.0 supercomputer at Institute of Science Tokyo."例3 (HPCIの例) 「本研究は、HPCIシステム利用研究課題 (課題番号:hp######) を通じて、
東京科学大学のスパコンTSUBAME4.0の計算資源の提供を受け実施した。」
"This work used computational resources of the TSUBAME4.0 provided by Institute of Science Tokyo through the HPCI System Research Project (Project ID: hp######)."2024年9月迄の利用による成果の場合は東京工業大学でも問題ありません。
例1 「本研究は、東京工業大学のスパコンTSUBAME4.0を用いて行った。」
"This study was carried out using the TSUBAME4.0 supercomputer at Tokyo Institute of Technology."例2 「全ての計算は、東京工業大学のスパコンTSUBAME4.0を用いて行った。」
"The numerical calculations were carried out on the TSUBAME4.0 supercomputer at Tokyo Institute of Technology."例3 (HPCIの例) 「本研究は、HPCIシステム利用研究課題 (課題番号:hp######) を通じて、
東京工業大学のスパコンTSUBAME4.0の計算資源の提供を受け実施した。」
"This work used computational resources of the TSUBAME4.0 provided by Tokyo Institute of Technology through the HPCI System Research Project (Project ID: hp######)."