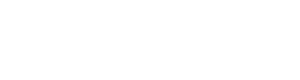採択情報
令和7年度、令和6年度、令和5年度、令和4年度、令和3年度、令和2年度、平成31年度、平成30年度、平成29年度、平成28年度、平成27年度、平成26年度、平成25年度、平成24年度、平成23年度、平成22年度、平成21年度
令和5年度申請実績
| 利用区分 | カテゴリー | 応募数 | 採択数 |
|---|---|---|---|
| 学術利用 | 成果公開 | 26 | 26 |
| 産業利用 | 成果公開 | 0 | 0 |
| 成果非公開 | 10 | 10 | |
| 合計 | 36 | 36 | |
令和5年度 利用終了課題一覧
| 番号 | 所属機関 | 申請課題名 (課題概要) | 利用区分 (カテゴリー) | 状況 |
|---|
| 番号 | 所属機関 | 利用区分 (カテゴリー) | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大鵬薬品工業株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 2 | モジュラス株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 3 | 株式会社リコー | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 4 | 株式会社クレハ | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 5 | 中外製薬株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 6 | 中外製薬株式会社2 | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 7 | 住鉱資源開発株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 8 | 株式会社アグロデザイン・スタジオ | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 9 | 日東電工株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
| 10 | 協和キリン株式会社 | 産業利用 (成果非公開) | 終了 |
利用課題概要一覧
| 申請課題名 | 並列アプリケーションにおけるプロファイルおよびトレース予測手法の評価 |
| 利用課題概要 | 本研究課題では,並列アプリケーションを大規模実行した際のプロファイルおよび通信トレース収集に必要な時間コストと計算資源を削減するために当研究室で開発した,プロファイル予測手法と通信トレース予測手法の評価を行う. |
| 申請課題名 | 計算科学による Eudragit E PO の薬物可溶化メカニズムの評価 |
| 利用課題概要 | 難水溶性薬物の溶解性改善手法として、添加剤による可溶化が広く用いられている。近年、我々はアミノアルキルメタクリレートコポリマー (Eudragit EPO)が、強い薬物可溶化効果を示すことを見出した。さらに、その可溶化効果は溶液のpHによって大きく異なり、これは塩基性ポリマーであるEudragit E POのpH変化に伴う構造変化によると推察されているが、詳細は不明であった。そこで、本課題では、Eudragit E POの薬物可溶化メカニズムを明らかにすることを目的として、計算化学(主に分子動力学シミュレーション)を用いて、水溶液中の薬物とEudragit E POの相互作用を評価する。 |
| 申請課題名 | 粘性の温度依存性を考慮した乱流熱輸送現象のモデル化 |
| 利用課題概要 | 一般的な数値シミュレーションでは,動粘度をはじめとした物性値は一定値として取り扱われることが多い.しかし,燃焼など急激な温度変化を伴う流動場では,物性値が流体温度に応じて変化し,流動場に影響を及ぼす.そのような流動場を現実的なコストでシミュレーションするためには,物性値の温度依存性を考慮した乱流モデルが必要であるが,物性値の温度依存性が乱流場に与える影響は十分に理解されておらず,対応する乱流モデル・壁モデルも少ない.本研究は,粘性の温度依存性を考慮した乱流熱流動の直接数値解析を行い,物性値の温度依存性を考慮した乱流モデルの構築に必要な基礎的なデータベースを作成することを目的とする. |
| 申請課題名 | 固体酸化物電解セルにおける電極表面反応の第一原理計算 |
| 利用課題概要 | 温室効果ガスであるCO2をCOに変換できる固体酸化物形電解セル(SOEC)を用いたCO2電気分解が注目されている。しかし、SOECのCO2電気分解では,電極表面において酸化反応や炭素析出反応など望まない副反応を伴う場合が多く,その抑制が課題となっている。本研究では、第一原理計算を用いてCO2電気分解反応,カソードのCO2酸化反応,炭素析出反応を明らかにし、これら副反応を制御できる電極構造因子を明らかにする。 |
| 申請課題名 | 臨床情報統合データベースの機械学習解析 |
| 利用課題概要 | 課題責任者は日本大学医学部臨床情報統合データベースから医学的知見を抽出するために機械学習アルゴリズムを開発してきた。課題責任者のグループでは昨年度、情報処理の効率性に関してブレークスルーを与える新手法の開発と複数GPUを備えた大型計算機を最大限活用した大規模実装に成功した。そしてこれを用いてデータベースから薬剤効果判定や疾患進行予測を既存手法を超える精度で行うプロジェクトを策定し日本大学医学部倫理委員会において承認を得た。そこで、本共同利用課題を利用して実際に解析を進めるべくここに応募する。 |
| 申請課題名 | GPCRとシグナル分子の相互作用機構の分子動力学シミュレーション |
| 利用課題概要 | Gタンパク質共役受容体(GPCR)は細胞膜上に発現し細胞外側から細胞内側へシグナルを伝達する。このシグナル伝達はGPCRと他のシグナル分子が相互作用することで引き起こされており、GPCRの状態に応じて相互作用するシグナル分子が変化することで生体内におけるシグナル応答の変化をもたらしている。さらに、シグナル分子の活性化の程度もGPCRの置かれた環境に応じて変わることが知られている。本課題では、複数の状態をとりうるGPCRとそれに対応するシグナル分子との相互作用の動態を分子動力学シミュレーションによって明らかにし、状態依存的な相互作用をもたらす機構を探る。 |
| 申請課題名 | 超流動ヘリウムにおける量子乱流の数値的研究 |
| 利用課題概要 | 超流動とは非粘性の流れのことであり、量子凝縮系の物理学における重要な研究対象である。超流動の乱流は量子乱流ともよばれ、いまでも盛んに研究されている。量子乱流の長年の未解決問題として、T1-T2遷移という超流動の2段階乱流遷移がある。T1-T2遷移をシミュレーションするためには、大規模数値計算が必要だと考えられている。本利用課題では、TSUBAMEの性能を活用してそのような大規模数値計算を行い、量子乱流の重要な物理の解明を主な目標とする。 |
| 申請課題名 | MDシミュレーションと機械学習を用いた分子間相互作用の解析 |
| 利用課題概要 | 分子間相互作用は、材料開発から医薬品開発まで幅広い分野で重要な役割を果たしている。例えば、生物学的には、分子間相互作用がタンパク質機能や疾病に大きく関与している。本研究では、対象系の分子間相互作用をMDシミュレーションと機械学習を用いて特徴付ける手法を開発し、タンパク質系・材料系への応用を試みることを目的としている。分子間相互作用の特徴が明らかになることで、疾患の治療や新規材料の開発に貢献できると考えている。 |
| 申請課題名 | フェーズフィールド法と分子動力学法の連携による多結晶組織形成解析 |
| 利用課題概要 | 多結晶材料の高特性化のためには,製造工程における相変態,再結晶・粒成長などを通じた組織形成の高精度制御が鍵となる.本研究では,高効率な組織計算が可能な現象論的手法:フェーズフィールド法と,物性値等の入力不要で組織発展を扱える原子論的手法:分子動力学とをデータ科学により融合し,複数GPU並列計算を併用することで,原子レベルの物理を反映した大規模・定量的な多結晶組織予測を初めて可能とする.令和5年度は,前年度までに構築した純金属粒成長の大規模計算法および材料物性値の取得法を,固相変態や合金・機能材料などのより複雑な現象・系に適用できるよう拡張することで,計算駆動による多結晶組織制御の技術深化を図る. |
| 申請課題名 | 計算化学を利用した有機薄膜材料の構造解析 |
| 利用課題概要 | 次元性の有機薄膜材料は不溶性の場合が多い.ゆえに,有機化学における一般的な溶液での構造解析は困難である.従って,固体として測定したスペクトル情報と計算化学的なシミュレーションを組み合わせによって構造解析をおこなう必要がある.本課題では,我々がこれまでに合成した薄膜材料について,計算化学を用いたスペクトルシミュレーションの方法を開拓し,実験値との比較を用いた構造解析へと応用する. |
| 申請課題名 | 機能性ペプチド提示エクソソームの創製 |
| 利用課題概要 | エクソソームは、細胞から放出される50nmから150nmの細胞外小胞の一種である。エクソソームは、マイクロRNAやタンパク質などを内包しており、細胞間コミュニケーションツールとしての役割を果たしており、がん診断や薬物送達キャリアとしても注目されている。一方で、薬物キャリアとして活用するには、エクソソームを標的細胞に特異的に送達する必要がある。そこで、エクソソームの表面に機能性ペプチドを導入することで、新たな機能性エクソソームの創製を目指す。 |
| 申請課題名 | 低温電子顕微鏡4次元イメージング法の高度化 |
| 利用課題概要 | 低温電子顕微鏡実験データからタンパク質の構造変化をイメージングする「4次元イメージング法」を、実際の実験データに適用できるように高度化することを目指す。具体的には、(1) 実際の実験データに含まれるノイズに対応するために、プログラム「Noise2Void」を4次元イメージング法に取り込む、(2) タンパク質の構造変化だけでなく、構造変化に伴う自由エネルギー曲面を求めるために、分子動力学法の手法の1つである「アンブレラサンプリング法」を4次元イメージング法に取り込む。 |
| 申請課題名 | 深層学習を用いた分子動力学シミュレーションの高速化 |
| 利用課題概要 | タンパク質が持つ機能を解析するため、分子動力学シミュレーションによりタンパク質立体構造のダイナミクスを解析する研究が広く行われている。しかしながら、分子動力学シミュレーションには大きな計算コストを必要とするという問題点があり、長時間・大規模なシミュレーションを行うにはスーパーコンピュータを用いても膨大な時間を要する。そこで本課題では、深層学習をベースとしたデータ駆動型のアプローチを用いることで分子動力学シミュレーションを高速に行う手法を開発し、効率的な大規模・網羅的シミュレーションの実現を目指す。 |
| 申請課題名 | 分子動力学シミュレーションによる新興再興感染症に関する研究 |
| 利用課題概要 | 易変異性RNAウイルスによる新興・再興感染症は、社会や経済に多大な損失をもたらす。そのため、その対策は世界が共有する公衆衛生上の重要課題になっている。我々は、計算科学により易変異性ウイルスの理解と制御に向けた基礎・応用研究を進めている。ウイルスの性質は、ウイルスタンパク質の構造により決定される。本研究では、TSUBAMEにおいてAmberによる分子動力学シミュレーションを実施し、変異がウイルスタンパク質の動的性質や宿主因子との相互作用に及ぼす効果を解析する。得られた情報を、病原体の性質変化の分子基盤解明、リスク評価、リスク変異予測、創薬標的同定、ワクチン抗原設計等に活用する。 |
| 申請課題名 | ナノ構造体を含むバルク材料のマルチスケール構造・熱輸送解析 |
| 利用課題概要 | 熱特性が異なるナノ粒子やナノワイヤ等を複合化し、放熱特性やエネルギー変換効率の向上を図る試みが注目されている。このような構造による熱伝導制御では単一のナノ構造体のみならず、ナノ構造体から成る階層構造など、異なる長さスケールにおける熱(フォノン)輸送を包括的に理解することが重要である。本研究課題では、原子・分子シミュレーションで求めたナノ構造体及びナノ構造体間のフォノン輸送の素過程をメゾスコピック熱輸送に組み込むことで、ナノ構造体とバルク材の熱伝導性の相関を明らかにするとともに高(低)熱伝導など工学的価値の高い熱機能材料の設計指針を得る。 |
| 申請課題名 | 量子アニーリングにおける近似的断熱ショートカット |
| 利用課題概要 | 量子アニーリングは,組合わせ最適化問題を量子効果によって解く手法として近年大きな注目を集めている.組み合わせ最適化問題をイジング模型として表現したとき,その基底状態から励起状態の非断熱遷移は量子アニーリングの性能の低下を招く.そのため非断熱遷移を抑制するためには十分長い時間をかけ量子アニーリングを行う必要がある.しかし現実のデバイスにおいては量子ビットのコヒーレンスタイムという律速があるため,短い時間で量子アニーリングを行う必要がある.本研究課題では量子アニーリングにおいて非断熱遷移を抑制する近似的カウンター項の構成を行い,量子アニーリング時間を短縮させるプロトコルを構築する. |
| 申請課題名 | 時空間並列アルゴリズムを用いた物理シミュレーション |
| 利用課題概要 | 利用課題の一番の目的は、超並列GPUコンピュータ用の新しい時空間局所化アルゴリズムの開発することである。これまで我々のアルゴリズムはメモリバウンド物理シミュレーション問題に既に利用されており、これには、ステンシルスキームなどのローカル依存関係を持つ数値スキームを用いることで様々な課題を解決してきた。これをさらに進めるためには、計算が処理順序やデータアクセス局所性、メッセージ通過速度などの更に多くの要因を考慮し、アルゴリズムの改良、検討を行う必要がある。研究対象を拡大することで時空間並列アルゴリズムを改良していくことが我々の研究テーマである。 |
| 申請課題名 | 深層生成モデルによる人工タンパク質設計 |
| 利用課題概要 | 本研究では、深層生成モデルと分子動力学シミュレーションを用いて、特定の作用をもつタンパク質をde novoで設計する技術を開発する。特に、特定のタンパク質モジュールを阻害する人工タンパク質に焦点を当て、ロボット技術と実験検証を組み合わせることで、これらのタンパク質を自動で設計、構築、検証、学習するプラットフォームを開発する。最終的に、設計されたタンパク質を用いた新たながん治療法の開発を目指す。 |
| 申請課題名 | 量子化学計算による水を酸化可能な近赤外吸収分子の探索 |
| 利用課題概要 | 色素増感太陽電池やバイオイメージングなど、近赤外光を利用する機能性分子の需要は高まっている。本課題では近赤外光を吸収する分子が光合成色素に代替可能かを、量子化学計算を用いて調べる。これまで広い条件で分子の光合成色素として重要な物性を調べており(Komatsu and Takizawa, PCCP, 2021)、これに引き続いて大きなπ共役系分子を対象に単量体、2量体の励起エネルギーや酸化還元的性質を推定する。計算結果を学習データにして機械学習によって水を酸化可能な近赤外吸収分子を提示するシステムを構築する。 |
| 申請課題名 | 機能性メタレンズのマルチスケール解析 |
| 利用課題概要 | 本課題では、機能性光メタレンズの設計に供するための、誘電体ナノ構造の光学的な応答解析を行う。現在、誘電体ナノ構造からなる可視波長域で動作するメタサーフェスレンズの開発を進めている。構造の最適化のためには光学特性の計算が必須であるが、必要なメモリが膨大となるため、従来所有していたワークステーションでは十分な計算を行えなかった。そこで、TSUBAME 3.0上でマルチフィジックス計算ソフトを利用することで、本課題の本格的な展開に取り組むことを目的として、申請を行った。2023年度には,偏光選択性を有するメタレンズに関するマルチスケール解析を行う。 |
| 申請課題名 | MDシミュレーションと量子化学計算を用いた医薬品開発支援 |
| 利用課題概要 | 本研究では、MDシミュレーションと量子化学計算を組み合わせた医薬品開発支援法を研究する。MDシミュレーションにより医薬品候補の物性を予測し、量子化学計算により分子の電子構造や反応性を評価する。TSUBAMEの高性能計算能力を活かし、複雑な分子システムの解析をおこない、医薬品の設計や効果予測に貢献する技術の確立を目指す。 |
| 申請課題名 | 溝付き超高速テイラー・クエット乱流の大規模数値解析 |
| 利用課題概要 | 省スペース,省資源,高効率化の観点から自動車用電動モータの高速回転化が求められている.モータのロータ・ステータには電磁場の最適化のために溝が設けられており,高速回転時にその間で誘起される流れが回転トルクの増大やステータコイルの発熱による問題を招くおそれがある.ロータ・ステータ間で生じる流れは,いわば溝付きのテイラー.クエット流れとみなすことができるが,超高速回転する溝付きのテイラー・クエット流れの熱流動現象は明らかにされていない.本研究では格子ボルツマンによる大規模並列乱流解析を行うことで構造が及ぼす影響を明らかにする. |
| 申請課題名 | 集風レンズ付き風車の中型200kw機とそのマルチロータシステムの技術開発 |
| 利用課題概要 | 高い発電性能を持つ風車として集風レンズ付き風車が注目されており,九州大学応用力学研究所では定格出力200kWの中型レンズ風車,およびその2基マルチロータシステムの技術開発を進めている.本利用課題では,数値流体シミュレーションにより,①台風などの強風時における風抵抗の評価と強風対策の検討,②2基マルチロータシステムの最適な風車隙間間隔の検討,③レンズ風車空力弾性解析に必要となる翼端損失モデルやディフューザー増速モデルの構築のための基礎データの取得,を行う. |
| 申請課題名 | GPUクラスタを用いたミリ波帯大規模広帯域電波伝搬シミュレーション |
| 利用課題概要 | ミリ波帯電波は他の周波数帯と比較して,電波の直進性が大きく,見通し伝搬の形態が多い。しかし,ひとたび電波伝搬のフレネルゾーン内に該当帯域電波の吸収体・散乱・反射体などが存在すると,受信電力の予測手法の複雑さが増大し,不確かさが大きくなる。また,ミリ波では,物質表面の凹凸の寸法が波長に比べて同程度となれば,その散乱特性がかなり影響を受ける.そこで,本研究では,屋内伝搬環境において受信電力を高精度に予測するために,大規模電磁界シミュレーションを新たに開発する。加えて,電波散乱壁やリフレクトアレーなどの反射体・散乱体を考慮できるようにする。 |
| 申請課題名 | 超多粒子焼結シミュレーションによるミクロ組織変化の統計的データ解析 |
| 利用課題概要 | 焼結で作製される多結晶材料の種々の特性は、内部のミクロ組織構造に依存する。そのため、熱処理中のミクロ組織変化を予測することを目的として、近年ではフェーズフィールド(PF)法を用いた数値シミュレーション手法の開発が活発化している。本研究では、世界最大規模の超多粒子系用いた固相焼結PFシミュレーションを実施する。これにより、焼結体の巨視的密度、粒径分布、結晶方位分布などの統計量の時間変化を明らかにするとともに、種々の材料物性値がこれらの統計量変化に及ぼす影響を調査する。 |
| 申請課題名 | 継続的ベイズ推論の改善 |
| 利用課題概要 | 深層学習では全てのデータが揃った状態で学習を行い、一度学習したモデルは更新できないのが一般的である。本利用課題では、継続的に学習しつづけるモデルの開発を目指す。また、継続的な深層学習に関する試みもいくつか存在するが、技巧的な手法を用いて経験的な性能向上を重視するものが多い。本利用課題では、数学的に厳密なベイズの原理に基づく理論により継続学習を根本的に見直すことを目的とする。ただし、ベイズ的な深層学習には通常の深層学習以上の膨大な計算量を要するため、TSUBAME3.0 のような大規模な計算資源が必要である。 |